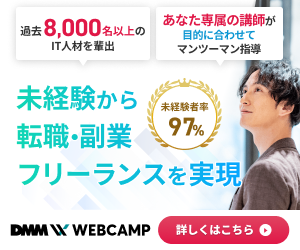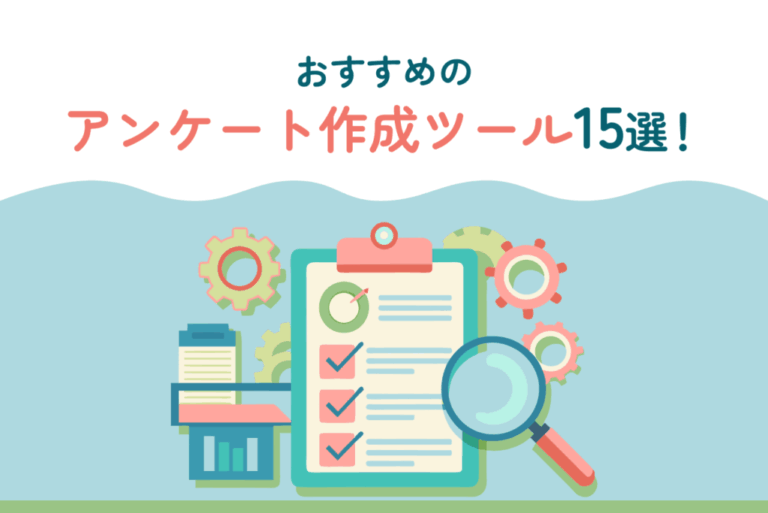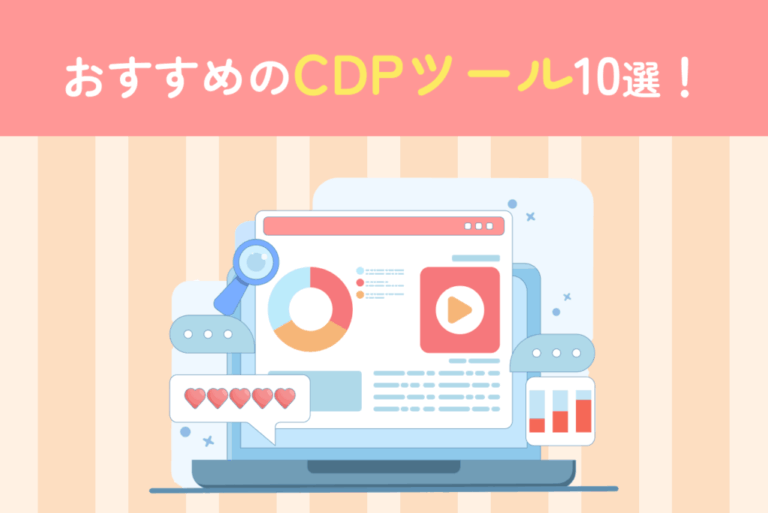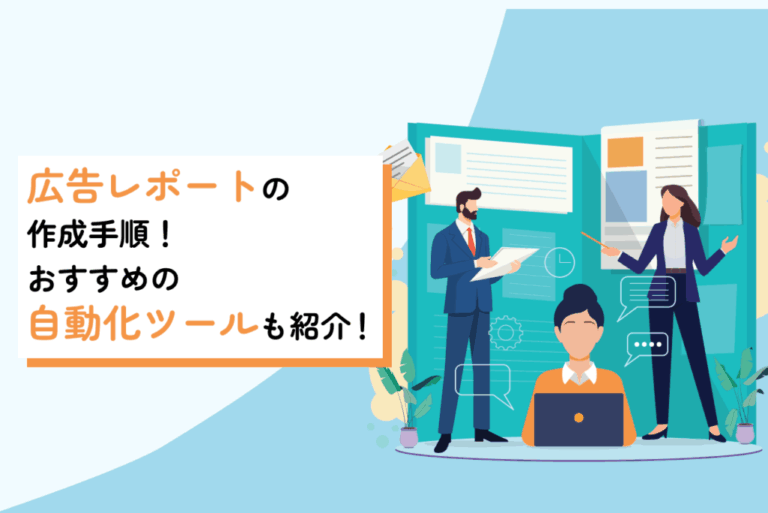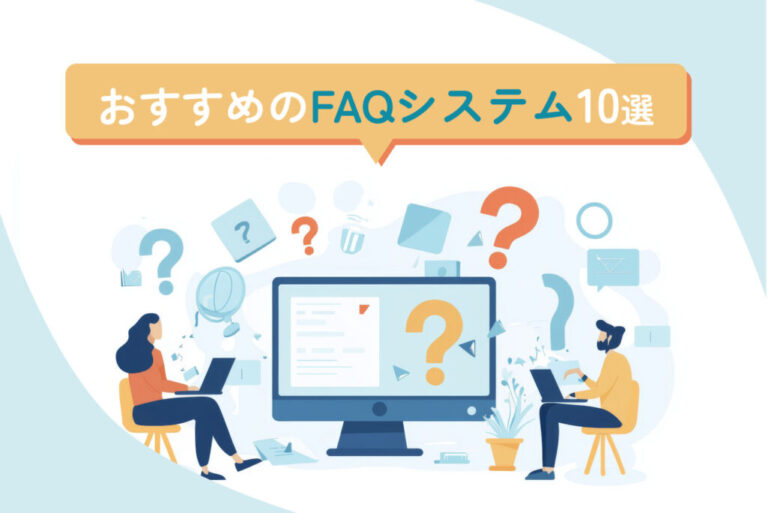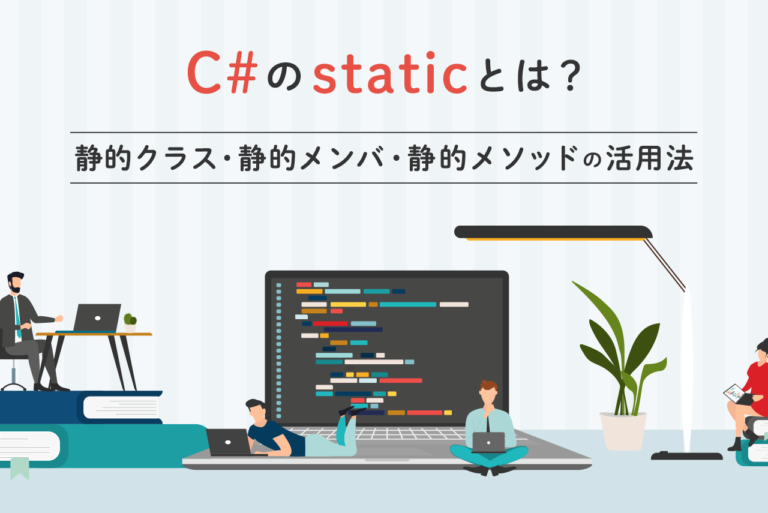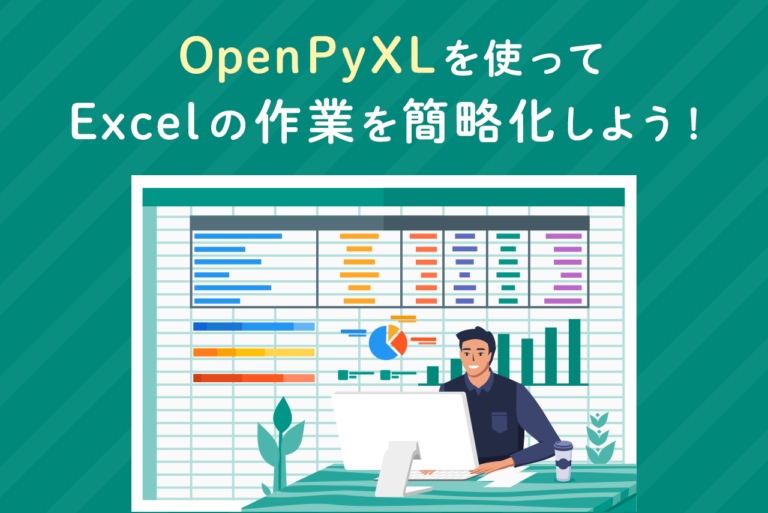企業のIT環境が多様化するなか、パソコンやソフトウェア、ライセンス、クラウドサービスなどのIT資産を適切に管理することは、業務の効率化やコスト削減、さらにはセキュリティ強化にも直結します。しかし、手動での管理では限界があり、情報の見落としや管理漏れがリスクにつながることも少なくありません。こうした課題を解決する手段として注目されているのが「IT資産管理ツール」です。
そこで今回は、導入メリットから選び方、おすすめのツールまで詳しく解説し、自社に最適な管理体制を築くためのヒントを提供します。
目次
- IT資産管理ツールとは
- IT資産管理ツールのメリット
- IT資産管理ツールのデメリット
- おすすめIT資産管理ツール10選
- IT資産管理ツールを選ぶ際のポイント
- IT資産管理ツールの導入手順
- IT資産管理ツールに関するよくある質問
- 自社の課題に合ったIT資産管理ツールを選定しよう
IT資産管理ツールとは

IT資産管理ツールは、企業内で利用されるコンピュータ、ソフトウェア、ネットワーク機器、ライセンス、クラウドサービスなど、幅広いIT関連資産を一元管理するためのソフトウェアです。導入することで、以下のような目的を達成することができます。
- 効率的な資産管理:手動での管理に代わり、リアルタイムで正確な情報を把握可能。
- コスト削減:不要なライセンス購入や未使用の資産を可視化し、最適化。
- セキュリティ強化:更新不足の資産やポリシー違反を早期発見して対処。
- コンプライアンス遵守:ライセンスや契約内容の適切な管理で法令違反を防止。
IT資産管理ツールは、手作業による台帳管理と比べ、効率性と精度が向上するため、企業規模が大きくなるほど導入メリットが高まります。
IT資産管理ツールのメリット

IT資産管理ツールは、ハードウェアやソフトウェアを効率的に管理し、業務効率化やコスト削減、セキュリティリスクの軽減に貢献します。これにより、企業はリソースを効果的に活用し、コンプライアンス強化や資産のライフサイクル管理を最適化することが可能になります。
ここでは、IT資産管理ツールのメリットについて解説します。
ハードウェア・ソフトウェアの一元管理で業務効率化ができる
IT資産管理ツールを導入することで、企業が保有するハードウェアやソフトウェアを一元的に管理できます。これにより、資産の把握や更新作業を効率化でき、重複購入や不要な資産の放置を防ぎます。
また、各デバイスのアップデート状況を把握し、必要なセキュリティパッチを迅速に適用することで、セキュリティ対策を強化します。例えば、最新のOSバージョンやウイルス対策ソフトの更新状況を一目で確認でき、人的ミスを減らすことが可能です。
このように、一元管理により業務の効率化が図れ、管理者の負担が軽減されます。
ITコストの最適化で無駄な支出を削減できる
IT資産管理ツールを活用することで、無駄な支出も削減できます。例えば、未使用のライセンスやデバイスを可視化することで、重複購入を防止し、必要な数だけを適切に調達できます。
また、資産の運用状況を正確に把握することで、不要なソフトウェアの利用を抑え、コストの削減が可能です。さらに、古くなったデバイスやサポートが終了したソフトウェアを特定し、計画的な更新や廃棄を行うことで、効率的なIT運用を実現します。このように、IT資産管理ツールは企業のコスト最適化に貢献します。
セキュリティリスクの低減とコンプライアンス強化
IT資産管理ツールは、セキュリティリスクの低減とコンプライアンス強化にも役立ちます。例えば、ソフトウェアライセンスの適正管理により、ライセンス違反を未然に防ぐことが可能です。
また、セキュリティパッチの未適用デバイスを自動的に検出し、迅速な対策を実施できます。さらに、操作ログの収集機能を活用することで、内部不正の抑止やセキュリティインシデント発生時の原因特定が可能になります。
これにより、情報漏洩やサイバー攻撃のリスクを大幅に軽減し、企業の信頼性を向上させることができます。
資産の適切なライフサイクル管理が可能になる
IT資産管理ツールを使用することで、資産のライフサイクルを適切に管理できます。導入から廃棄までの各段階で必要な管理を一元化し、資産の使用状況や更新時期を効率的に把握できます。これにより、不要な資産を適時に廃棄し、新規調達を最適化することで、資産の活用効率を向上させることが可能です。
さらに、リースやライセンスの契約期限を管理することで、更新漏れを防ぎ、無駄なコストや契約違反のリスクを回避できます。これにより、企業の資産運用がより計画的かつ効率的になります。
IT資産管理ツールのデメリット
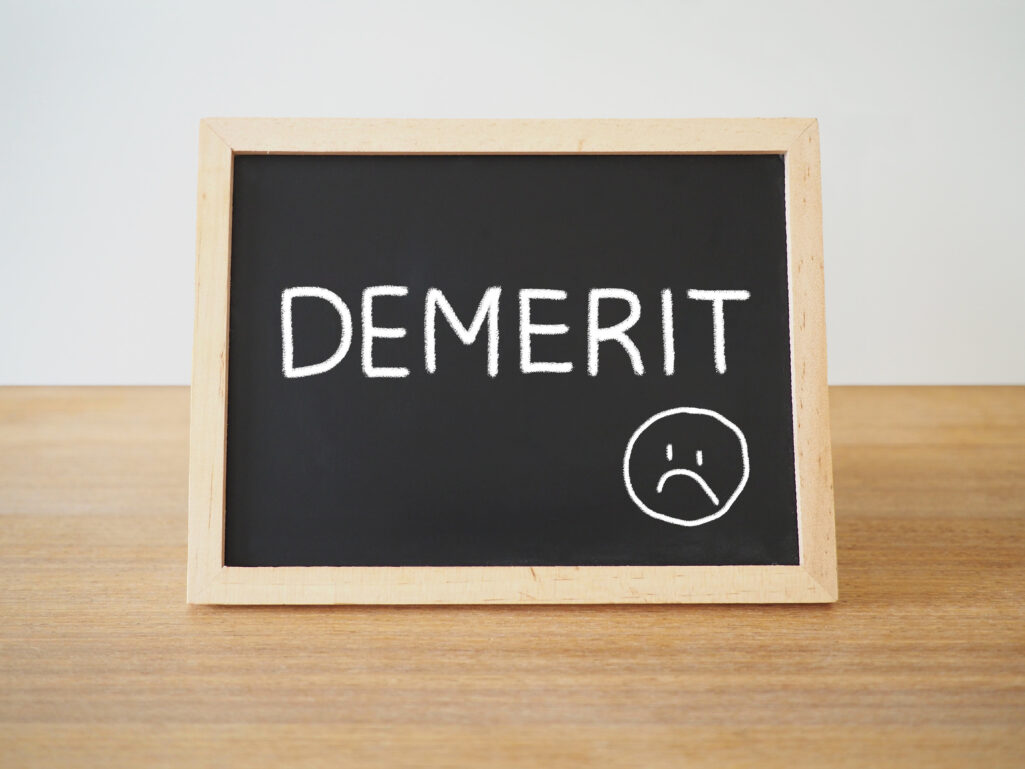
IT資産管理ツールは多くのメリットを持つ一方、導入や運用においていくつかのデメリットも存在します。特に初期費用や運用コストの高さ、専門知識の必要性、維持管理の手間、そしてセキュリティリスクへの対応が課題として挙げられます。
ここからは、IT資産管理ツールのデメリットについて解説します。
導入コストが高額になりがち
IT資産管理ツールの導入には高額なコストがかかることが一般的です。システムそのものの費用に加え、インフラ整備や必要なハードウェアの購入、さらに従業員のトレーニングコストも発生します。また、特定のカスタマイズや追加機能が必要な場合、その分の費用も上乗せされるため、初期投資が予想以上に膨らむことがあります。
導入後も、システムの運用・保守に関連するコストが継続的に発生します。特に中小企業ではこれらの費用が負担となりやすいため、コスト対効果を十分に検討することが重要です。クラウド型のサービスを選択することで初期費用を抑える選択肢もありますが、ランニングコストとのバランスを考慮し、導入を検討しましょう。
設定や運用に専門知識が必要
IT資産管理ツールを効果的に活用するには、専門知識が求められる場面が多々あります。初期設定ではシステム環境に適した導入計画の策定や、既存システムとの連携のための技術的な調整が必要です。また、日常的な運用においても、ツールの操作方法やトラブルシューティングの知識が求められます。
さらに、新しい機能の追加やツールのバージョンアップに対応するためには、継続的な学習が欠かせません。その結果、IT部門の負担が増大する可能性があります。運用をスムーズにするためには、導入前に十分なトレーニングを行い、必要に応じてベンダーからのサポートを受けることが重要です。
維持管理に手間がかかることもある
IT資産管理ツールを維持するためには、定期的なシステム更新やデータの見直しが必要です。特に、使用状況やデバイスの状態に基づいてデータを更新し続ける作業は、非常に煩雑になりがちです。また、新たなデバイスやソフトウェアが追加された場合、これらをツールに適切に登録し、管理するプロセスが発生します。
さらに、管理対象となる資産の増加に伴い、システムのパフォーマンスが低下するリスクもあります。そのため、ツールのスムーズな動作を確保するために、追加のリソースを投入する必要が出てくることがあります。
システム障害やデータ漏洩のリスクがある
IT資産管理ツール自体がシステム障害やデータ漏洩のリスクを伴う場合があります。特にクラウド型のツールを利用する場合、外部サーバーへの依存度が高いため、サービス提供元の障害やサイバー攻撃の影響を受ける可能性があります。また、不適切なアクセス制御や設定ミスにより、管理している資産データが流出するリスクも考えられます。
これらのリスクを軽減するためには、ツールの導入前にセキュリティ要件を十分に確認し、信頼性の高いサービスを選ぶことが重要です。また、運用中にも定期的なセキュリティチェックやバックアップの実施が求められます。これにより、万が一の事態に備えることが可能となります。
おすすめIT資産管理ツール10選

IT資産管理ツールは、企業のIT資産を効率的に管理し、セキュリティリスクを軽減するために欠かせない存在です。ここでは、用途や規模に応じて選べる、おすすめのIT資産管理ツール10選をご紹介します。導入に迷っている方は、特徴や価格を比較し、自社に最適なツールを見つけてみてください。
| ツール名 | 特徴 | 強み/用途 | 価格プラン |
|---|---|---|---|
| SKYSEA Client View | 使いやすさとセキュリティ対策を両立 | 大規模から小規模まで対応。情報漏洩対策や運用管理に強み | 問い合わせにて要確認 |
| System Support best1(SS1) | 高いカスタマイズ性と直感的操作が可能 | 資産管理やセキュリティ対策を効率化し、多様なオプション機能を提供 | 1ライセンス5,000円~ |
| AssetView | コストパフォーマンスが高い統合管理 | 中小規模の企業に最適。セキュリティや操作ログ管理も対応 | 問い合わせにて要確認 |
| LANSCOPE エンドポイントマネージャー | 情報漏洩対策と多彩なデバイス管理が可能 | AI活用の脅威検知が強み。PC・スマホの一元管理が可能 | 月額300円/台~ |
| PalletControl | 大規模なPC運用管理に特化 | 自動化による運用コスト削減。セキュリティ管理も対応 | 問い合わせにて要確認 |
| MaLion 7 | Mac端末の管理に特化した一元管理ツール | WindowsとMacの管理が可能。内部不正対策も強化 | 問い合わせにて要確認 |
| ISM CloudOne | クラウド型でセキュリティリスクを可視化 | テレワークに最適。多国籍企業での利用実績あり | 問い合わせにて要確認 |
| MCore | 大規模企業向けの統合管理システム | 大規模導入に適した拡張性とスケーラビリティ | 問い合わせにて要確認 |
| QND Premium | 中小企業向けのセキュリティ特化ツール | 簡単な操作でセキュリティ管理と資産管理を実現 | 問い合わせにて要確認 |
| Freshservice | IT資産管理とヘルプデスク機能を統合 | AI活用で自動化を実現。多機能なITSMプラットフォーム | 問い合わせにて要確認 |
SKYSEA Client View|使いやすさとセキュリティ強化を両立

出典:https://www.skyseaclientview.net/
SKYSEA Client Viewは、企業や団体が直面するIT資産管理やセキュリティの課題を解決するためのツールとして、多くの実績を誇っています。特に導入数22,650ユーザー(2024年11月現在)という規模は、信頼性の高さを物語っています。このツールは、オンプレミス版とクラウド版の両方を提供しており、利用者のニーズに応じて柔軟に選択可能です。
その特長の一つは、情報漏洩対策の強化です。標的型攻撃やランサムウェアへの対応策として、多層的なセキュリティ機能を備えており、USBデバイス管理や暗号化機能、外部との通信ログ取得などが挙げられます。また、MacやLinux対応を含む幅広いOS環境での利用が可能で、定期的なバージョンアップにより、時代のセキュリティ要件に対応しています。
さらに、PC1台から最大50,000台まで管理可能な拡張性や、検索性に優れた管理画面により、管理者の負担を軽減します。これにより、運用の効率化とセキュリティの両立が可能です。企業のIT資産管理とセキュリティ強化を両立させるための頼れるツールとして、多様な業界で高い支持を得ています。
System Support best1(SS1)|カスタマイズ性に優れたツール
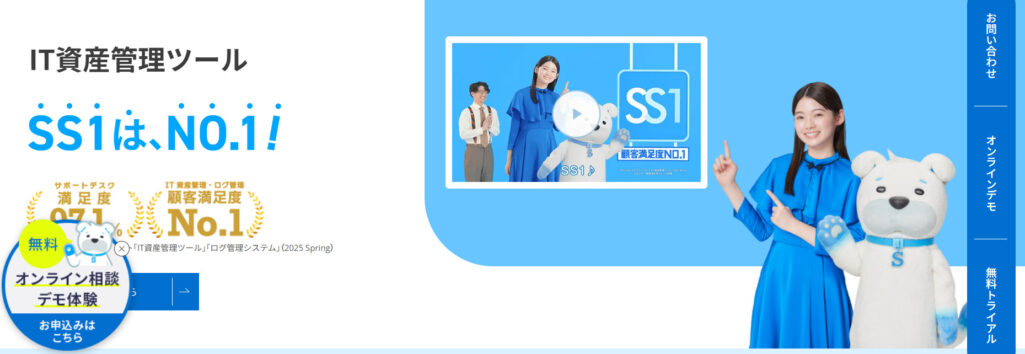
出典:https://www.dos-osaka.co.jp/ss1/
System Support best1(SS1)は、IT資産管理ツールの中でも特にカスタマイズ性に優れており、企業の多様なニーズに柔軟に対応できる点で評価されています。このツールは、基本的な資産管理機能に加え、必要なオプション機能を選択して導入できる統合型ソリューションです。企業規模を問わず利用可能で、3,900社以上の導入実績(2024年1月時点)を誇ります。
SS1の特徴の一つは、直感的に操作可能な管理画面です。Excelに似たインターフェースを採用しており、PCやサーバー、ソフトウェアの状況を一目で把握できます。また、ログ収集やデバイス制限など、企業のセキュリティを強化する多彩なオプション機能が用意されています。特に、クラウド型やオンプレミス型の選択肢があるため、企業のIT環境やセキュリティポリシーに応じて導入することが可能です。
さらに、サポート体制の充実もSS1の強みです。導入時にはサーバー構築や操作レクチャーなどの支援を提供し、導入後も定期フォローやユーザー専用サイトによる情報提供が行われます。このように、運用のしやすさと高度なカスタマイズ性を兼ね備えたSS1は、企業のIT資産管理を効率化する強力なパートナーといえるでしょう。
AssetView|コストパフォーマンスに優れたIT統合管理

出典:https://www.hammock.jp/assetview/
AssetViewは、業種や規模を問わず、多くの企業で導入されているIT資産管理ツールです。その最大の特長は、コストパフォーマンスの高さと、統合的なIT運用管理機能を兼ね備えている点です。大手企業から教育機関、地方自治体まで幅広く採用されており、特に効率性を求める企業に支持されています。
このツールは、外部からの脅威対策としてウイルスやマルウェアの検知・駆除、重要な情報漏洩を防ぐファイル持ち出し制御機能を備えています。また、セキュリティアップデートを容易に管理できる機能も提供されており、Windows OSの更新プログラムやブラウザのバージョン管理を一元的に実施できます。これにより、脆弱性を狙ったサイバー攻撃への対応力が向上します。
さらに、操作ログの取得や不正操作の監視により、内部からのリスク対策も万全です。必要な機能だけをライセンス購入する柔軟性があるため、初期費用を抑えつつ、長期的な運用コストの削減も可能です。オンプレミス版とクラウド版の選択ができ、企業のニーズや規模に応じた導入が実現します。
このように、AssetViewは、高機能と経済性を兼ね備えたIT資産管理ツールとして、多くの企業の課題解決に貢献しています。
参考:AssetView
LANSCOPE エンドポイントマネージャー|情報漏洩対策に強い

出典:https://www.lanscope.jp/endpoint-manager/
LANSCOPE エンドポイントマネージャーは、PCやモバイルデバイスを一元管理できるIT資産管理ツールで、特に情報漏洩対策に優れた機能を提供しています。このツールは、クラウド型とオンプレミス型の選択肢を持ち、10,000社以上の導入実績を誇ります。セキュリティ対策と効率的な管理を両立させたい企業にとって、信頼できるソリューションです。
LANSCOPEの特長は、AIを活用した高度な脅威検知機能です。未知の脅威を99%防御する「予測脅威防御」により、従来のウイルス対策では防げなかったサイバー攻撃にも対応します。また、操作ログの取得やアラート管理により、内部リスクの早期発見と対応が可能です。ログデータは最大5年間保存でき、企業のコンプライアンス強化にも貢献します。
さらに、Apple Business ManagerやAndroid Enterpriseに対応し、iOSやAndroidデバイスの管理も簡単に行えます。これにより、スマートフォンやタブレットを含むあらゆるデバイスを一元管理することができます。加えて、クラウド型のシンプルな導入プロセスと操作性の高い管理コンソールにより、初めての導入でも安心して利用できます。
LANSCOPE エンドポイントマネージャーは、強固なセキュリティ対策と柔軟な管理機能を提供し、企業の情報漏洩リスクを最小限に抑えるための頼れるパートナーです。
PalletControl|大規模PC運用に特化した自動化ツール

出典:https://www.jalinfotec.co.jp/solution/palletcontrol/
PalletControlは、大規模なPC運用管理を効率化するために開発されたIT資産管理ツールです。JALグループのPC管理を28年以上にわたり支えてきた実績があり、信頼性と実用性の両面で高く評価されています。
PCのキッティングや初期設定の自動化をはじめ、IT管理者の業務負担を軽減するさまざまな機能を搭載。資産管理・配布管理・セキュリティ対策・ユーザーサポートという4つの主要機能を標準で備えており、PC情報やソフトウェアライセンスの一元管理が可能です。さらに、日々変動する情報を自動的に取得し、管理業務の効率化を実現します。
ソフトウェア配布や設定変更の自動化により、運用コストを抑えながら迅速な対応が可能になります。また、デバイスの制御や持ち出しログの監視機能によって、セキュリティリスクを最小限に抑える設計です。
ユーザーサポート面では、リモート接続やチャット機能を活用したスムーズな対応が可能で、トラブル対応の迅速化にも貢献します。必要に応じて多彩なオプション機能を追加でき、各企業の運用スタイルに合わせた柔軟なカスタマイズが行えます。
PC運用をより簡単に、効率的かつ安全に進めたい企業にとって、PalletControlは信頼できるソリューションといえるでしょう。
MaLion 7|Mac端末の管理に強い一元管理ツール
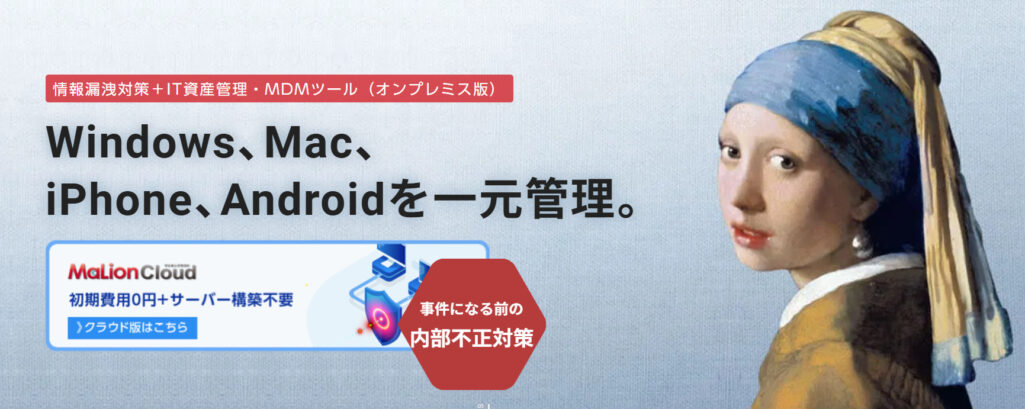
出典:https://www.intercom.co.jp/malion/7/
MaLion 7は、WindowsとMacの両方のOSを一元的に管理できるIT資産管理ツールです。特にMac端末の管理に優れており、オンプレミス環境での運用を前提に設計されています。情報漏洩対策やIT資産管理、労務管理までを総合的に支援するソリューションです。
本ツールの特長の一つが、操作性に優れた管理コンソールです。直感的に操作できるUI設計により、管理者は日常業務をスムーズに進められます。また、端末操作のログを詳細に記録し、不正操作や情報漏洩リスクの早期発見にも貢献します。さらに、印刷制限や外部デバイスの接続制限といったセキュリティ機能も標準で備えています。
なかでも、Mac端末に対する操作制限機能は他社製品よりも高く評価されており、業務でMacを多用する企業にとって心強い選択肢となります。加えて、Windows端末の管理機能も充実しており、混在環境における一元管理を実現します。
また、テレワーク環境を見据えたリモート管理機能や、勤怠管理システムとの連携機能も搭載。従業員の働き方を可視化し、業務の効率化と透明性の向上に貢献します。
Mac端末を積極的に活用している企業にとって、MaLion 7は最適なIT資産管理ツールといえるでしょう。
参考:MaLion 7
ISM CloudOne|クラウド型でセキュリティリスクを自動診断

ISM CloudOneは、世界55か国以上で利用されているクラウド型のIT資産管理・セキュリティ対策ツールです。インターネット環境さえあれば、社内外を問わず端末の一元管理が可能であり、特にセキュリティリスクの可視化に優れています。
セキュリティ状態をグラフで直感的に表示できるダッシュボードを搭載しており、端末の問題点を一目で把握できます。脆弱性診断、操作ログの取得、外部デバイスの制御、BitLocker管理、URLフィルタリングといった多彩な機能を備えており、テレワーク環境でも安心して導入できます。
クラウド型であることを活かし、VPNを使用せずに遠隔地のPCやスマートデバイスの管理が可能です。端末ごとのセキュリティ更新プログラムの診断や、ウイルス対策ソフトの稼働状況の確認、未対応の脆弱性に対するアラート通知といった機能により、IT管理者の負担を軽減します。
さらに、テレワーク中の勤務状況を可視化できる機能もあり、PCの稼働状況や操作ログをリアルタイムで確認することができます。ISM CloudOneは、グローバルに事業を展開する企業やリモートワークを積極的に活用する企業にとって、強固なセキュリティと高い管理効率を両立する有力な選択肢といえるでしょう。
参考:ISM CloudOne
MCore|大規模企業向けのIT資産統合管理ツール

出典:https://www.sei-info.co.jp/mcore/
MCoreは、大規模企業向けに設計されたIT資産管理ツールです。セキュリティ管理やコンプライアンスの推進を一元的に支援し、住友電工グループでは10万台を超える端末管理に活用された実績があります。信頼性と拡張性の両立に優れたソリューションといえます。
このツールの特長は、1台のサーバーで数百台から1万台超の端末まで柔軟に対応できるスケーラビリティです。国内外の拠点に点在するIT資産も一括管理できるため、グローバル展開している企業にも適しています。さらに、クライアント端末に導入されるエージェントは軽量で、業務への影響を抑えた設計が施されています。
MCoreには、インベントリ管理、ソフトウェア配布、パッチ管理、ログ管理、デバイス制御など、20種以上の機能が搭載されています。なかでも、最新パッチの自動配布や不正なデータ持ち出しの防止といったセキュリティ対策は強化されており、情報漏洩のリスク軽減に寄与します。
また、多言語対応にも力を入れており、英語や中国語での表示に加え、海外OSの管理にも対応。企業の規模や業種を問わず、IT資産の最適な運用と堅牢なセキュリティ体制を実現できるツールとして、多くの導入実績を誇ります。
参考:MCore
QND Premium|中小企業に最適なIT資産管理ツール

出典:https://www.qualitysoft.com/product/lineup/qnd_premium_standard/
QND Premiumは、中小企業向けに特化したIT資産管理ツールです。コスト効率に優れ、幅広いセキュリティ対策機能を備えている点が特長です。1998年のリリース以来、多くの企業に導入されており、シンプルながらも強力な機能により高い評価を受けています。
最大の特長は、ハイブリッドクラウド型で提供されていること。オンプレミスとクラウドの両方を活用することで、社内外問わずIT資産の一元管理が可能です。操作ログの取得、外部デバイスの制御、URLフィルタリングといった高度なセキュリティ機能も標準で搭載されており、情報漏洩リスクの軽減や不正行為の早期発見に役立ちます。
さらに、自動脆弱性診断機能を備えており、OSやソフトウェアの更新状況、ウイルス対策ソフトの状態などをチェックできます。クイックリモコン機能を利用すれば、ネットワーク経由でのリモート操作も容易で、ヘルプデスク業務の効率化につながります。
必要な機能を柔軟に選択できる仕組みのため、導入コストを抑えつつ、企業のセキュリティ水準を高めることが可能です。中小企業が抱えるIT資産管理の課題に対応する、信頼性の高いソリューションといえるでしょう。
参考:QND Premium
Freshservice|IT資産管理とヘルプデスク機能を統合

出典:https://www.freshworks.com/jp/
Freshserviceは、IT資産管理とヘルプデスク機能をひとつのプラットフォームに統合したITサービスマネジメント(ITSM)ツールです。AIを活用した自動化機能により、IT部門の業務を効率化します。
本ツールの大きな特長は、コード不要で利用できるドラッグ&ドロップ形式のワークフロー構築機能です。これにより、インシデント管理・変更管理・問題管理といったITSMプロセスを迅速かつ柔軟に構築・運用することができます。また、統合CMDB(構成管理データベース)によってIT資産間の関係性や依存関係を可視化し、より的確な意思決定を支援します。
さらに、チケット管理やアラート管理、ナレッジマネジメントといった多彩な機能を備えており、IT部門の業務運用を支えるだけでなく、従業員やエンドユーザーへの迅速な対応も実現します。Microsoft TeamsやSlack、Zoomといった主要なツールと連携できる点も魅力です。チーム間のコミュニケーションをスムーズにし、業務全体の生産性向上につながります。
Freshserviceは、IT資産管理の枠を超え、組織全体の業務効率化とサービス品質の向上を図りたい企業に適した選択肢といえるでしょう。AIによる自動化と統合的な管理機能を活かし、IT業務を戦略的な価値創出へと導きます。
参考:Freshservice
IT資産管理ツールを選ぶ際のポイント

IT資産管理ツールの選定は、企業における効率的なIT運用やセキュリティ強化において欠かせない要素です。ここでは、最適なツールを見極めるうえで押さえておきたい重要なポイントをわかりやすく解説します。自社の課題やニーズを踏まえ、最適な選定につなげていきましょう。
導入目的を明確にし、必要な機能を洗い出す
IT資産管理ツールを導入する際には、まず「何のために活用するのか」という目的を明確にすることが欠かせません。たとえば、ライセンス管理の最適化やセキュリティリスクの低減、内部統制の強化など、企業によって求められる役割は異なります。
目的を具体的に定めることで、必要な機能が見えてきます。インベントリ収集、ライセンス管理、ログ収集などは、それぞれ異なる課題に対応するものです。どの機能を優先すべきかを明らかにしたうえで、自社の課題に合ったツールを選ぶことが、導入効果を高めるカギとなります。
自社のIT環境に対応しているか確認する
IT資産管理ツールは、自社のIT環境に適していることも重要です。導入時には、使用しているハードウェアの種類やオペレーティングシステム(Windows、macOS、Linuxなど)、さらに導入済みのソフトウェアの構成を考慮する必要があります。
たとえば、Windows端末が多い場合は、Windows管理に強みを持つツールが有効です。スマートフォンやタブレットを業務に活用している企業では、モバイルデバイス管理(MDM)機能が充実しているツールが適しています。
自社の現状を正しく把握し、それに合ったツールを選ぶことで、IT資産の運用効率やセキュリティ対策の効果を高めることができます。
クラウド型とオンプレミス型の違いを理解する
IT資産管理ツールには、大きく分けてクラウド型とオンプレミス型の2種類があります。クラウド型はインターネット経由で利用でき、初期費用を抑えられる点が魅力です。リモートワークや複数拠点での活用にも向いており、柔軟な運用が可能です。
一方、オンプレミス型は社内サーバーにツールをインストールして使用します。ネットワークに依存せずに運用できるため、セキュリティ要件が厳しい企業や独自のカスタマイズが必要な場合に適しています。
それぞれに利点と課題があるため、自社の運用環境やセキュリティ要件、予算を踏まえて、最適な提供形態を選ぶことが大切です。
セキュリティ機能の充実度を確認する
IT資産管理ツールを選定する際は、セキュリティ機能の充実度も重要な判断基準となります。不正アクセスや情報漏洩を防ぐには、最新のセキュリティパッチを迅速に配布できる機能を備えたツールが適しています。
また、デバイス制御や禁止ソフトウェアの起動制御といった機能も見逃せません。これらにより、業務に不要なアプリケーションの使用を抑制し、セキュリティリスクの低減につながります。
加えて、操作ログの取得機能を活用することで、不正な操作やセキュリティポリシー違反を素早く検知できます。ログデータに基づいたアラート通知やリスク判定機能を備えたツールを選ぶことで、問題発生時にも迅速な対応が可能になります。
企業の規模や利用環境に応じたセキュリティ機能を備えるツールを選ぶことが、堅牢な情報管理体制の構築につながります。
使いやすさと管理画面の操作性をチェックする
IT資産管理ツールを効果的に活用するには、操作性の高さが欠かせません。なかでも、管理画面の見やすさや使いやすさに優れたツールは、日常の管理業務を効率化するうえで大きな助けとなります。
たとえば、デバイスやライセンスの状況を一目で把握できるダッシュボードや、直感的に操作できるUIを備えたものは、管理の負担を軽減します。
さらに、ITに詳しくない担当者でも扱いやすいツールを選ぶことで、業務の属人化を防ぐことができます。機能が豊富であっても操作が複雑すぎるツールは避け、日々の運用がスムーズに行えるものを選ぶことが、継続的な活用につながります。
費用対効果を考慮して選ぶ
IT資産管理ツールを選ぶ際には、費用対効果を慎重に見極めることも重要です。初期導入費用だけでなく、運用やメンテナンスにかかるコストも含めて総合的に検討しましょう。
たとえば、クラウド型のツールは月額料金が発生しますが、サーバーの設置や保守が不要なため、結果として運用コストを抑えられる場合があります。これに対してオンプレミス型は、導入時の初期投資が大きくなりがちですが、長期的な運用ではコストを抑えられるケースもあります。
さらに、必要以上に多機能なツールを選んでしまうと、利用しない機能が増えるだけでなく、コストも無駄にかさみやすくなります。導入の目的を明確にし、必要な機能に絞って選定することが、コストパフォーマンスを高めるポイントです。
IT資産管理ツールの導入手順

IT資産管理ツールを効果的に導入するには、各ステップを丁寧に進めることが欠かせません。まずは現状のIT環境を正確に把握し、課題を明確にすることが第一歩となります。そのうえで、社内の関係者と連携しながら目的や要件を整理し、導入後の運用体制も視野に入れて進めることが求められます。ここでは、現状分析から関係者との調整、そして実際の導入に至るまでのプロセスをわかりやすく解説します。
1.現状のIT資産管理状況を把握する
IT資産管理を始めるうえでの第一歩は、自社にあるIT資産の現状を正確に把握することです。現在使用しているハードウェアやソフトウェア、そのライセンスの状況まで確認しましょう。エクセルや専用の管理ツールを使って情報を一覧化すれば、作業効率が高まります。
あわせて、未使用の機器や過剰に取得されたライセンスを特定することで、無駄なコストの削減にもつながります。こうした作業は、今後の管理体制を整えるうえで欠かせない基盤となります。
2.導入の目的と要件を明確にする
ツールを導入する際は、目的と必要な要件を明確に定義することも重要です。たとえば、コストの削減、セキュリティの強化、コンプライアンスの遵守など、達成したい目標を具体的に設定します。
目的が定まったら、それに対応する機能をリストアップし、必要な条件を満たす製品を選定する指針とします。こうした準備を行うことで、導入後のミスマッチや失敗のリスクを抑えることができます。
3.社内の関係部署と要件をすり合わせる
IT資産管理ツールを円滑に導入するには、関係部署との綿密なコミュニケーションも重要です。情報システム部門をはじめ、経理部門や人事部門など、ツールの活用に関わる各部署と連携し、それぞれが抱える課題や導入への期待を共有しておきましょう。
たとえば、経理部門では資産台帳の正確な管理が求められ、人事部門では入退社に伴うIT資産の引き渡しや回収業務の効率化が課題となることがあります。こうした要件を事前に丁寧にすり合わせておくことで、導入後の混乱や手戻りを防ぎやすくなります。
4.IT資産管理ツールを選定する
市場には多くのIT資産管理ツールが存在しており、その中から自社に最適なものを選ぶには慎重な検討が必要です。エージェント型かエージェントレス型かといったツールのタイプや、搭載されている機能を比較することが重要なポイントになります。
たとえば、セキュリティ機能の充実度、対応可能なデバイスの種類、サポート体制の質などを確認しましょう。さらに、過去の利用者によるレビューや、提供元ベンダーの信頼性にも目を通しておくと安心です。こうした点を総合的に確認することで、導入後のトラブルや失敗を防げます。
5.無料トライアルやデモで実際に試す
ツールを導入する前に、無料トライアルやデモ版を活用して、実際の操作感も確かめましょう。この段階では、現場の担当者にも試用してもらい、操作性や機能が期待に沿うかを評価することが大切です。
特に、ツールが実際の業務フローに適応できるかどうか、また導入による負荷が過剰にならないかを確認しておく必要があります。こうしたプロセスを踏むことで、導入後のスムーズな定着につながります。
6.ベンダーと導入計画を策定する
選定したツールのベンダーと連携し、導入計画を具体的に策定します。計画には、導入スケジュールや予算、必要なリソースを明記することが欠かせません。加えて、ベンダーのサポート体制も事前に確認しておきましょう。初期設定やトラブル発生時に、どの程度の支援が受けられるかが重要な判断材料になります。
また、導入作業に支障が出ないよう、関係部署とのスケジュール調整も計画段階で行っておく必要があります。円滑な導入を実現するためには、各部門との連携が不可欠です。
7.システムの初期設定とデータ移行を実施する
導入したツールの初期設定を実施し、必要なデータを移行します。初期設定では、資産台帳の作成やネットワークに接続された機器の登録を行うことが基本です。
また、過去のデータを正確に移行することは、運用開始後の精度や信頼性に直結します。そのため、ベンダーのサポートを受けながら作業を進めることで、効率よく確実に対応することが可能です。
さらに、設定作業中に生じる不具合や疑問点をその場で解消するためにも、ベンダーとの緊密な連携が欠かせません。
8.社内トレーニングと運用体制の構築
ツール導入後は、現場スタッフを対象にトレーニングを実施し、運用体制を整えます。トレーニングでは、基本的な操作方法や注意すべき運用ルール、トラブル発生時の対応方法などを丁寧に解説します。
あわせて、ツールの管理責任者を明確にし、運用フローを文書化しておくことも重要です。これにより、ツールの活用が社内に定着し、スムーズな運用が実現します。
トレーニング後も、定期的なフォローアップを計画することで、運用レベルの維持と課題の早期発見につなげられます。
9.導入後のテスト運用と調整を行う
本格運用に先立ち、ツールのテスト運用を実施し、必要な調整を行います。この段階では、実際の業務フローにツールを組み込み、運用上の課題や不具合を洗い出すことが目的です。操作性の問題、データ反映の遅延、利用者間の連携不足などが代表的な課題として挙げられます。
発見された問題には、ベンダーと連携して迅速に対応し、改善を図ります。テスト運用を十分に行うことで、本格運用後のトラブルを未然に防ぐことが可能です。
10.本格導入と定期的な運用・評価を開始
テスト運用で得られた改善点を反映しながら、ツールの本格導入を進めます。運用開始後も、定期的な評価を実施し、必要に応じて運用方法の見直しを行います。評価項目としては、コスト削減の効果や業務効率化の進捗、セキュリティ強化の実績などが挙げられます。
さらに、利用者からのフィードバックを継続的に収集し、使いやすさを高める運用体制を整えることが求められます。こうした取り組みを積み重ねることで、ツール導入の効果を最大限に引き出すことが可能となります。
IT資産管理ツールに関するよくある質問

IT資産管理ツールは、企業が保有するハードウェアやソフトウェアなどのIT資産を、効率的かつ的確に管理するために欠かせない存在です。ここでは、IT資産管理ツールに関して寄せられることの多い質問を取り上げ、それぞれ丁寧に解説します。
IT資産管理ツールとは何ですか?
IT資産管理ツールとは、PCやサーバー、プリンター、ネットワーク機器、ソフトウェアライセンスなど、企業内にあるすべてのIT資産を一元的に管理するためのシステムです。このツールを導入することで、各資産の状態や利用状況を可視化でき、適切な配備や廃棄の判断を効率的に行えます。
さらに、セキュリティリスクの軽減やコストの最適化にも貢献します。近年では、クラウド型とオンプレミス型の両方が提供されており、自社の環境や目的に応じて柔軟に選択・運用することが可能です。
IT資産管理ツールの市場シェアは?
IT資産管理ツールの市場は年々拡大しており、特にクラウド型ツールの普及が加速しています。市場調査会社の予測によると、2024年には前年比10%以上の成長が見込まれ、国内外で注目を集めています。
代表的なツールには「SS1」や「SKYSEA Client View」などがあり、それぞれに特長があります。国内市場では、中小企業を中心にコストパフォーマンスの高いツールが選ばれる傾向にあります。対して、大企業では多機能性や他システムとの統合性を重視するケースが多く見られます。
自社の規模や業務内容に応じて、最適なツールを選定することが成功へのカギとなります。
IT資産管理ツールの費用はどれくらいかかりますか?
IT資産管理ツールの費用は、選ぶツールの種類や搭載されている機能によって大きく異なります。一般的に、クラウド型ツールは月額制が多く、1ユーザーあたり500円から数千円程度で利用できます。
一方、オンプレミス型では、初期費用として数十万円から数百万円かかることもあります。加えて、サポート費用やオプション機能の追加料金が発生する場合もあるため、導入後のランニングコストにも注意が必要です。
費用対効果を見極めたうえで、自社の予算や業務内容に適したツールを選定しましょう。
クラウド型とオンプレミス型、どちらを選べばよいですか?
クラウド型とオンプレミス型のどちらを選ぶべきかは、企業の規模やITインフラの構成、そしてセキュリティ要件によって判断が分かれます。
クラウド型は初期投資が少なく、導入や運用の手間も比較的少ないことから、中小企業やスピーディーな導入を求める企業に適しています。インターネット環境さえあればすぐに利用を開始できる点も魅力です。
一方、オンプレミス型は自社サーバー上でシステムを運用するため、より高度なカスタマイズが可能であり、情報管理やセキュリティの厳格な対応が求められる大企業に向いています。
それぞれのメリットと課題を比較したうえで、自社の目的や体制に合った形態を選択することが重要です。
自社の課題に合ったIT資産管理ツールを選定しよう

IT資産管理は、業務効率の向上やコスト削減、セキュリティの強化に直結する重要な取り組みです。この記事で紹介したツールや選定のポイントを参考に、自社の課題や運用体制に合った最適なツールを見極めてください。
目的や企業規模に応じた製品を導入すれば、管理の負担を軽減し、IT環境を持続的に最適化することが可能になります。これを機に、IT資産管理の見直しに取り組んでみてはいかがでしょうか。